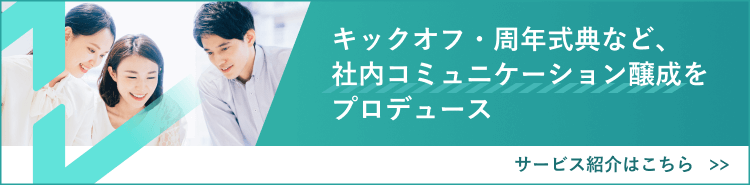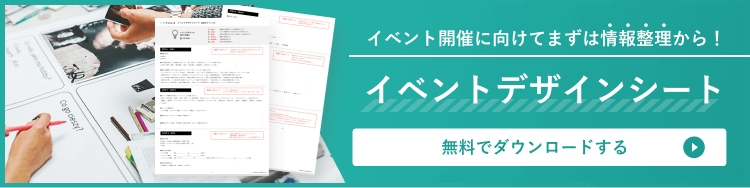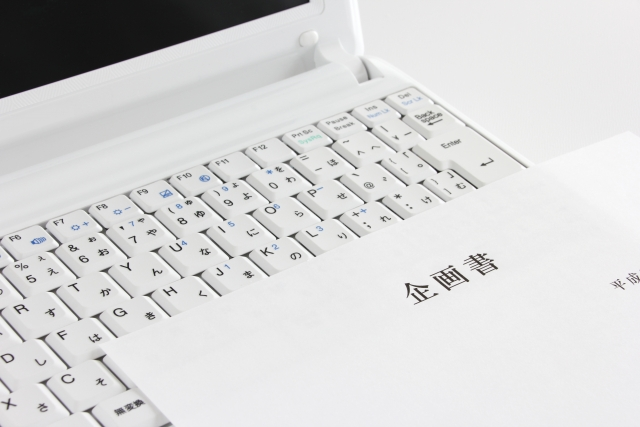福利厚生費を社内懇親会に利用する条件や事例とは?

新年会や忘年会などの社内懇親会を開いている企業は多いのではないでしょうか。
社内懇親会を開く際には支出される食事代やイベント代などの費用について会社が負担する場合も多くみられます。そのような会社経費として計上する場合、勘定科目として使われるのが福利厚生費です。
ただし、全ての会社負担を福利厚生費として計上できるわけではなく、その利用には一定のルールがあります。
今回は福利厚生費を社内懇親会に利用する条件や事例についてわかりやすく解説します。
目次
社内懇親会の開催を福利厚生費で行える条件
社内懇親会の費用は、一定の条件を満たせば「福利厚生費」として計上できます。ただし、全ての懇親会が認められるわけではなく、税務上のルールを正しく理解することが大切です。ここでは、福利厚生費として計上するための主な条件を解説します。
- 全社員または合理的な単位の全員を対象とすること
- 福利厚生や親睦が目的であること
- 社会通念上妥当な金額であること
- 参加者ごとに差をつけないこと
- 必要な証拠書類を整備すること
全社員または合理的な単位の全員を対象とすること
社内懇親会の費用を福利厚生費として計上するためには、原則として、全社員を対象としていることが求められます。
ただし、事業所単位や部署単位など、業務の実態に応じた合理的な区分での開催であれば、全社員でなくても福利厚生費として認められます。例えば、営業部の懇親会であれば、部内全員を対象としていれば、福利厚生費として認められるわけです。
一方で、役員のみや特定の少人数だけを対象とした懇親会は、福利厚生費として認められません。
福利厚生や親睦が目的であること
福利厚生費として認められるためには、懇親会の目的が従業員の福利厚生や職場の親睦・コミュニケーションの促進であることが求められます。つまり、社員同士の交流やチームビルディングなど、従業員のために行われる行事であることが大前提です。
後述しますが、もし懇親会に取引先や外部の関係者が参加している場合、福利厚生費ではなく交際費となります。
社会通念上妥当な金額であること
福利厚生費として計上できる費用は、社会通念上妥当と認められる範囲内であることが条件です。実務では一人あたり5,000円前後が参考とされるケースが多いですが、具体的な上限は法律で定められていません。なお、費用の目安や具体的な考え方については後ほど詳しく解説します。
参加者ごとに差をつけないこと
社内懇親会で福利厚生費として認められるためには、参加者ごとに提供する内容や金額に大きな差があってはいけません。例えば、役職や立場によってコース料理のグレードを変える、特定の人だけ豪華な食事を用意するなどは、福利厚生費としては認められません。
必要な証拠書類を整備すること
社内懇親会を福利厚生費として計上する際は、領収書や帳簿などの書類が必要です。
例えば、参加者名簿や領収書はもちろん、開催日時・場所・懇親会の内容や目的などが記載された帳簿など、開催実態を証明できる資料をきちんと揃えておくことが大切です。
税務調査が行われた際に、これらの書類を求められるケースも多いため、日頃から適切に保管・管理しておきましょう。

福利厚生費として計上できる社内懇親会の費用の目安
社内懇親会の費用を福利厚生費として計上する場合、法律で明確な上限は定められていません。これまで実務では「一人あたり5,000円前後」が目安とされてきましたが、令和6年度の税制改正により「交際費などから除外される飲食費」の上限が1万円に引き上げられています。そのため、今後はこの金額も一つの参考になるでしょう。
ただし、福利厚生費の判断基準は金額だけではありません。同業他社の相場や会社の規模、懇親会の内容なども総合的に考慮され、「社会通念上妥当な範囲かどうか」がポイントとなります。そのため、常識的な金額・内容にとどめておくのが安心です。
ニューズベースでは、社内懇親会の開催における福利厚生費の取扱いや実務に関するご相談も承っています。判断に迷われた場合はお気軽にご相談ください。
社内懇親会の勘定科目をケース別に紹介
社内懇親会の費用は、開催の仕方や対象によって「福利厚生費」または「交際費」として処理する必要があります。ここでは、ケースごとに適切な勘定科目の判断ポイントを紹介します。
福利厚生費として計上できる社内懇親会の例
・全社員を対象とした懇親会(例:新年会・忘年会)
社員全員が参加できる社内懇親会の場合、その費用が常識的な範囲内であれば福利厚生費として処理できます。
・部署単位など合理的な区分で行う懇親会
部署ごとなど業務上合理的な単位で実施し、全部署が対象で金額の差も大きくない場合は、全社員対象でなくても福利厚生費として認められます。
交際費として処理すべき社内懇親会の例
・特定の少人数や役員だけの懇親会
会社全体や部署単位ではなく、特定の人だけで行われる懇親会や役員のみの集まりの場合は、福利厚生費にはできず、交際費として計上するのが原則です。
・取引先や外部関係者が参加する場合
懇親会に取引先や社外の関係者が加わっている場合も、その費用は交際費となります。
福利厚生費で行える社内懇親会の例
福利厚生費に算入できる社内懇親会の条件について、具体的な事例をみていきましょう。
全社員で参加する社内懇親会の場合
社員全員を対象とした社内懇親会として新年会や忘年会などの経費を会社が支出する場合は、その金額が通常の飲食に要する範囲内であれば福利厚生費として損金算入することができます。
部署単位で行われる社内懇親会の場合
社員全員でなくても部署ごとに社内懇親会を実施した場合でも、全部署が対象となっており、また支出した一人当たりの金額にも大きく差がない場合は福利厚生費として経費算入しても問題ありません。
少人数で行われる社内懇親会の場合
特定の人間だけで行われる懇親会の負担については、会社の全従業員を対象としたものではないので福利厚生費として計上することができません。ただし会社が催した社内懇親会の飲食費であっても接待交際費として処理することができる場合があるので確認するのがよいでしょう。
社内懇親会には準備が必要
参加する社員の労いやモチベーションを向上させるような魅力のある社内懇親会を開催するには相応の準備が必要になります。
例えば福利厚生の一環として全社員を対象とした新年会や忘年会などの社内懇親会を開く場合は、社員が一堂に会することができるようなホテルやイベント会場などの場所が必要になります。
また、飲食の手配や場合によってはイベントなども催す場合もあるのではないでしょうか。
事前準備をしっかりと行うことができれば、社員の参加率も高めることができるだけでなく、会社に対するロイヤルティを高める効果もあります。
懇親会の準備や運営を請け負う企業も存在する
社内懇親会の準備や運営が大切なことはわかりましたが、それらの業務を社内の人間が通常業務の合間をぬって対応するのは負担が大きいものです。
また、せっかく社内懇親会を開催するのであれば、参加者に満足感を与えることができる有意義な懇親会にしたいと思うのではないでしょうか。
そのような場合には、社内懇親会の準備や運営を請け負っている企業があるので相談してみるのも一つの方法です。
社内懇親会の準備や運営を請け負うニューズベースであれば、これまでにさまざまな企業の社内イベントの準備から運営までを請け負ってきたノウハウがあり、利用した企業の満足度も高いサービスを展開しています。
これまでニューズベースが手がけた社内イベントに関するノウハウ記事を展開しているので、まずは確認してみることをおすすめします。

5.まとめ
今回は社内懇親会と福利厚生費の関係について具体例を交えて説明しました。
社内懇親会を開く際に支出される食事代などの費用については、参加者や開催条件などによって福利厚生費として計上できる場合と、その他の勘定科目で計上する必要がある場合があります。
この記事を読むことで福利厚生費を社内懇親会に利用する条件や事例について理解して社員にも会社にとってもメリットを持たせるだけでなく、社内懇親会の準備や運営のノウハウがある企業なども活用しながら有意義な社内懇親会を開くようにしましょう。