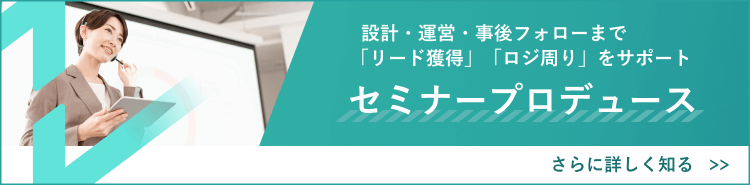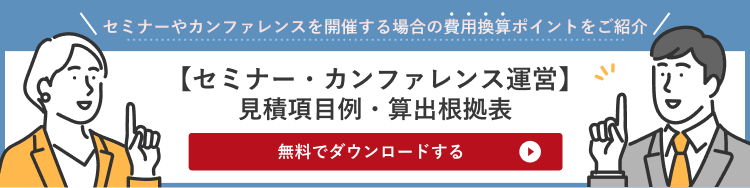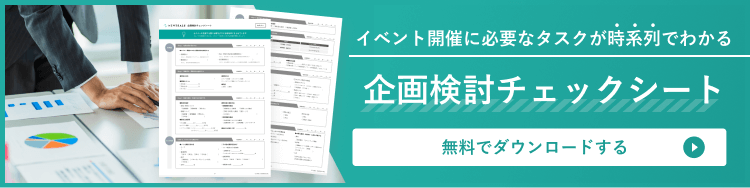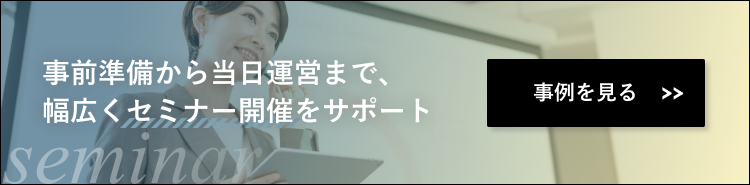ウェビナー資料を作成する上で意識すべきポイント5選!構成内容や作成手順も

ウェビナーが成功するかどうかは、資料のクオリティ次第といっても過言ではありません。
そのため、どのようなことに気をつけて資料を作成すればいいのか、気になる担当者も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、ウェビナー資料を作成する上で意識すべきポイントや作成手順について解説します。
目次
ウェビナーと通常のセミナーの資料の違い
ウェビナーと通常のセミナーの資料の違いとして、以下の2点が挙げられます。
- 配布方法
- 配布形式
表で簡単にまとめてみました。
| ウェビナー | 通常のセミナー | |
| 配布方法 | ・オンライン上でダウンロード ・リアルタイムでの画面共有 |
・会場で直接配布 ・スクリーン上で共有 |
| 配布形式 | スライドまたはビデオ | スライドまたは紙での資料 |
ウェビナーと通常のセミナーの資料では、上記のような違いがあるので、覚えておきましょう。
ウェビナー資料の基本的な構成内容
ウェビナー資料の基本的な構成内容は、以下の通りです。
- 冒頭
- ウェビナーの内容
- サービスや商品の紹介
- アクションしてもらいたい内容の説明
ウェビナー資料を作成する上で、必ず覚えておきましょう。順番に解説します。
冒頭
まずは冒頭です。冒頭部分は、以下の5つに細分化されます。
- 表紙
- ウェビナー中の注意事項
- 自己紹介
- ウェビナーで学習する内容
- 目次
表紙はウェビナーが始まる前から表示されるため、タイトルや開始時間・担当者の名前などを記載しましょう。
ウェビナーの内容
ウェビナーの内容は、ウェビナー資料を作成する上で最も重要な部分です。
このクオリティ次第で、ウェビナーが成功するかどうかが変わってくるため、慎重に作成する必要があります。
作成する上で意識すべきポイントついては、後ほど詳しく解説します。
サービスや商品の紹介
ウェビナーを開催する企業の多くが、「サービスや商品の認知度を高めたい!」「1人でも多くのユーザーから自社のサービスや商品を購入してもらいたい!」と思っているはずです。
そのため、ウェビナーが終了する前にサービスや商品の紹介を行いましょう。
ただし、セールストークを嫌がるユーザーも一定数いるため、あまり時間をかけ過ぎないことが大切です。
アクションしてもらいたい内容の説明
ウェビナーの最後には、ユーザーにアクションしてもらいたい内容の説明を行います。
具体的には、アンケートの回答や資料請求などが挙げられます。
ウェビナー資料の作成手順
ウェビナー資料の作成手順は、以下の3ステップです。
- ウェビナーの開催目的やターゲットを明確にする
- 構成について考える
- ダブルチェックやリハーサルを行う
一つずつ解説します。
1.ウェビナーの開催目的やターゲットを明確にする
ウェビナー資料を有益なものにするためには、開催目的やターゲットが明確に決まっていなければなりません。
ウェビナーの開催目的やターゲットは企業によって異なるため、まずは「なぜウェビナーを開催する必要があるのか」「どのようなユーザーをターゲットにすべきなのか」について、明確化していきましょう。
2.構成について考える
ウェビナーの開催目的やターゲットを明確にしたら、構成について考えます。
構成は、前項で解説した以下の内容に沿って順番に決めていきましょう。
- 冒頭
- ウェビナーの内容
- サービスや商品の紹介
- アクションしてもらいたい内容の説明
3.ダブルチェックやリハーサルを行う
構成について考えたら、最後にダブルチェックやリハーサルを行います。
ダブルチェックは、上司や同僚にしてもらいましょう。
リハーサルに関しては、時間に余裕がある限り何度でも行い、万全の体制で本番を迎えましょう。
ウェビナー資料を作成する上で意識すべきポイント5選
ウェビナー資料を作成する上で意識すべきポイントとして、以下の5つが挙げられます。
- 画像や動画は積極的に挿入する
- 文字のサイズは24pt以上にする
- 伝えたい内容は1スライドにつき1つに絞る
- アニメーションを使い過ぎない
- 共有用と配布用の2種類の資料を用意しておく
順番に解説します。
画像や動画は積極的に挿入する
画像や動画は、テキストよりも情報量が多くインパクトがあるので、ユーザーの記憶にも残りやすくなります。
そのため、ウェビナー資料を作成する際には、テキストだけでなく画像や動画を積極的に挿入するようにしましょう。
文字のサイズは24pt以上にする
ウェビナー資料を作成するにあたって、文字のサイズには注意が必要です。
文字のサイズが小さいとユーザーは読むのに苦労してしまい、内容を理解するまで時間がかかるからです。
大きすぎず小さすぎないちょうどいい文字のサイズとして、24pt以上を目安にしましょう。
伝えたい内容は1スライドにつき1つに絞る
少しでも多くの情報をユーザーに伝えるために、1つのスライドに大量の情報を詰め込んでしまうと、ユーザー側は何を伝えたいのかが理解できない恐れがあります。
また、同じ資料の状態で長時間説明するので、ユーザーは次第に飽きてしまい、集中力の低下にもつながります。
そうならないようにするためにも、伝えたい内容は1スライドにつき1つに絞るということを徹底しましょう。
アニメーションを使い過ぎない
ウェビナー資料にアニメーションを使うことで、強調したい部分をアピールできたりメリハリをつけたりするなどのメリットに期待ができます。
しかし、アニメーションの使い過ぎは逆効果となる恐れがあります。
アニメーションは特に強調したい部分のみに絞り、多用しないようにしましょう。
共有用と配布用の2種類の資料を用意しておく
資料によっては、当日のウェビナーに参加したユーザー限定の内容を記載していることもあるはずです。
そのため、当日の資料をそのまま配布してしまうと、何かしらのトラブルが起こる可能性があります。
トラブルを未然に回避するためにも、共有用と配布用の2種類の資料を用意しておきましょう。
まとめ
本記事では、ウェビナー資料を作成する上で意識すべきポイントや作成手順について解説しました。
ウェビナーと通常のセミナーの資料では、配布方法や配布形式が異なります。
ウェビナーが成功するかどうかは、資料のクオリティ次第といっても過言ではないので、ウェビナー資料を作成する際には画像や動画を積極的に挿入したり、伝えたい内容は1スライドにつき1つに絞ったりすることなどを意識しましょう。
ウェビナーを開催するにあたって、「開催経験が乏しくリソースも不足していることから、自社でウェビナーを開催できるか不安」という企業もいるのではないでしょうか。
そのような場合には、株式会社ニューズベースにお任せください。
株式会社ニューズベースでは、セミナープロデュースサービスを提供しており、セミナーやウェビナーに関するさまざまな業務のサポートを行っています。
そのため、現状のリソースでも開催することが可能です。
また、豊富な支援実績もあり業務におけるプロが担当するため、セミナーやウェビナーの開催経験が乏しくても安心です。
まずはお気軽にお問い合わせください。