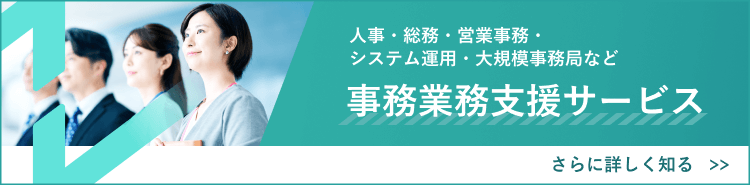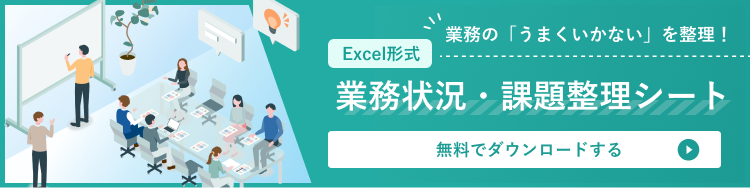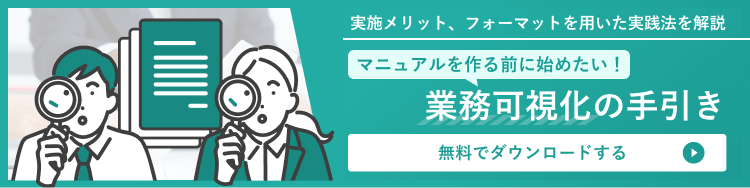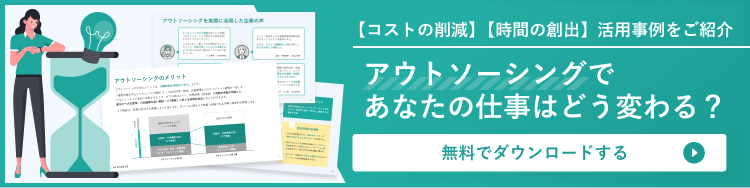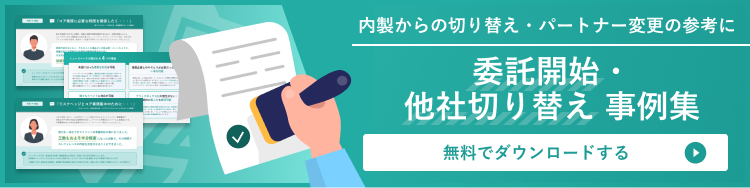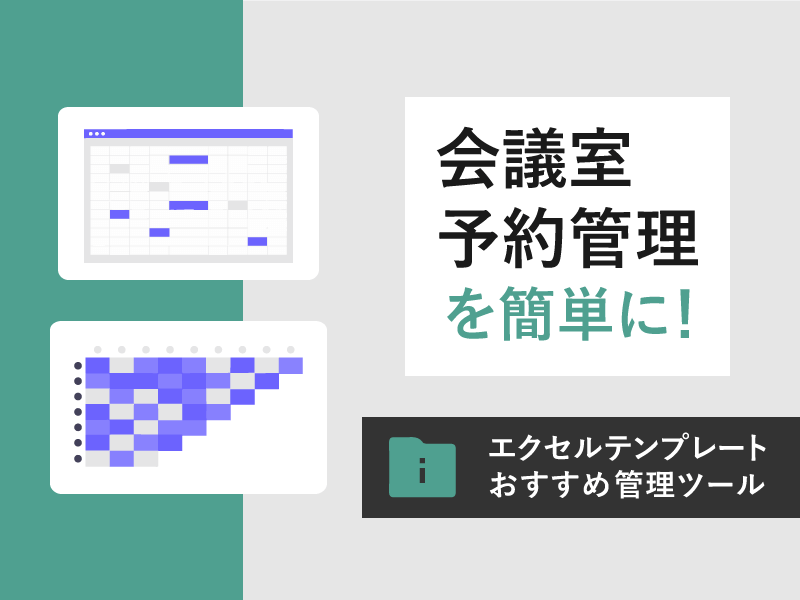業務改善の4原則とも呼ばれる「ECRS」とは?活用するメリットやデメリットなどを解説!

これから業務改善を実施するのであれば、業務改善の4原則とも呼ばれる「ECRS」を活用するのがおすすめです。
ECRSについて、名前は聞いたことがあっても意味についてあまり把握していないという方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、ECRSの基礎知識や活用するメリット・デメリット・業務改善でECRSを成功させるためのポイントについて解説します。
目次
業務改善の4原則とも呼ばれる「ECRS」とは?
業務改善の4原則とも呼ばれる「ECRS」とは、以下の頭文字を取ってできたフレームワークのことです。
- Eliminate(排除:複数の業務や作業をまとめて一つにできないか)
- Combine(結合:複数の作業や手順を結合できないか)
- Rearrange(交換:作業の順序や手段・担当者などを入れ替えて効率化できないか)
- Simplify(簡素化:業務内容や手順をよりシンプルにできないか)
業務改善においてECRSを活用することで、生産性の向上やコストの削減など、さまざまな効果に期待ができます。
なお「E」が最も改善効果が大きく、「S」が最も改善効果が小さい傾向にあります。
業務改善でECRS(業務改善の4原則)を活用するメリット
業務改善でECRSを活用するメリットは、以下の通りです。
- 生産性の向上に期待ができる
- コストの削減につながる
- ヒューマンエラーを防止できる
- 属人化を解消できる
順番に解説します。
生産性の向上に期待ができる
ECRSを活用することで、無駄な作業や重複した業務を取り除くことができます。
その結果、本当に必要な作業や業務だけが残ります。
取り除いた分のリソースを別の業務に充てることで、生産性の向上に期待ができるでしょう。
コストの削減につながる
ECRSによって、不要な業務を排除したり作業を結合したりすることができるため、人的リソースや設備コストを大幅に削減することが可能です。
削減したことで浮いた資金やリソースをほかの重要業務や新規事業に充てることで、企業のさらなる発展につながるはずです。
ヒューマンエラーを防止できる
ECRSを活用することで、業務をシンプルかつ合理的にしたり自動化したりすることが可能です。
その結果、ヒューマンエラーの防止につながります。
ヒューマンエラーの防止によって、これまで以上に業務品質が高まり、顧客満足度の向上にも期待ができるでしょう。
属人化を解消できる
ECRSの活用によって業務手順を簡素化・標準化できるため、誰もが同じクオリティで作業が行えるようになり、属人化の解消につながります。
属人化が解消されることで業務マニュアルの作成やナレッジの蓄積が可能となり、特定の従業員が仮に休んだとしても業務を滞りなく遂行できるようになります。
業務改善でECRS(業務改善の4原則)を活用するデメリット
業務改善でECRSを活用することによって、メリットだけでなくデメリットも生じます。
主なデメリットは以下の通りです。
- 時間や労力がかかる
- チーム全体や関係部署から理解を得る必要がある
- 品質低下のリスクがある
一つずつ解説します。
時間や労力がかかる
ECRSを活用して業務改善を行うためには、現状の業務プロセスやタスクを詳細に洗い出して、課題を特定する必要があります。
このような作業には膨大な時間や労力がかかり、とても一朝一夕では行えません。
特に属人化した業務や複雑な工程が多い場合には、通常よりも時間や労力がかかるため、注意が必要です。
これらのことから、人手不足が常態化している企業の場合には、通常業務と並行して作業を行うのが難しく、従業員にも大きな負担がかかるでしょう。
チーム全体や関係部署から理解を得る必要がある
ECRSによる業務改善は、特定の業務だけでなくチーム全体や関係部署の業務フローにも大きな影響を与えます。
そのため、ECRSによる業務改善を実行するにあたって、チーム全体や関係部署から理解を得なければいけません。
周知が不十分だったり理解が得られなかったりする状態で業務改善を行ってしまうと、現場の混乱や反発・雰囲気の悪化など新たな問題を生む可能性があるため、十分に気をつけましょう。
品質低下のリスクがある
業務の簡素化や削減を進めるあまり、本来必要なチェックや工程まで省略してしまう可能性があります。
その結果、品質低下のリスクがあるため、注意が必要です。
また、業務を標準化しすぎることで、現場の柔軟性や対応力が損なわれる場合もあるため、臨機応変に対応することが求められます。
業務改善でECRS(業務改善の4原則)を成功させるためのポイント
業務改善でECRSを成功させたいのであれば、以下のポイントを意識しましょう。
- 目的を明確にする
- 長期的な施策だと考える
- 企業全体で取り組む
順番に解説します。
目的を明確にする
業務改善でECRSを活用するにあたって、目的が定まっていないと必要な作業を排除してしまったり、業務を結合したことで逆に煩雑化したりするなどのリスクがあります。
このような事態を防ぐためにも、目的を明確に設定するようにしましょう。
明確な目的を設定することで、ECRSを活用した業務改善の方針が定まり、具体的な行動計画へと落とし込めます。
長期的な施策だと考える
業務改善を実施するには、少なくとも以下のような手順を踏まなければいけません。
- 目的・目標の明確化
- 現状業務の可視化・分析
- 課題・ムダの抽出
- ECRSの4原則による改善策の検討
- 改善案の立案・実行計画の策定
- 関係者への説明・合意形成
- 実行・定着化
- 効果検証・PDCAサイクル
数多くの手順を踏む必要があるため、決して短期的ではなく長期的な施策だと考えるようにしましょう。
企業全体で取り組む
業務改善を実施するにあたって、経営層だけで目標や計画を設定したとしても、実行するのは現場で働く従業員です。
そのため、業務改善でECRSを成功させたいのであれば、経営層から現場の従業員まで一致団結して企業全体で取り組むことが大切です。
経営層だけでなく現場の従業員も交えた上で目標や計画を明確化し、業務改善の意図や効果を周知して協力体制を整えましょう。
まとめ
本記事では、ECRSの基礎知識や活用するメリット・デメリット・業務改善でECRSを成功させるためのポイントについて解説しました。
業務改善でECRSを活用することで、生産性の向上やコストの削減・ヒューマンエラーの防止・属人化の解消に期待ができます。
ただし、時間や労力がかかったり、チーム全体や関係部署から理解を得る必要があったりするなどのデメリットもあるので、注意が必要です。
業務改善でECRSを成功させたいのであれば、目的を明確にして長期的な施策であると考えた上で、企業全体で取り組むようにしましょう。
株式会社ニューズベースでは事務業務支援サービスと業務伴走支援サービスを提供しております。
事務業務支援サービスでは、業務マニュアルの作成や問い合わせ対応・データ入力・営業資料の作成などをサポートし、
業務伴走支援サービスでは、現状の可視化・標準化などをはじめとする改善・マニュアル化から、改善後の定期的な状況見直しまでお客様に伴走したサポートを行います。
これまで中小企業から大手企業・大学・官公庁まで、業界業種問わずにサービスを提供してきたため、安心して依頼いただけます。
無料見積もりを行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。