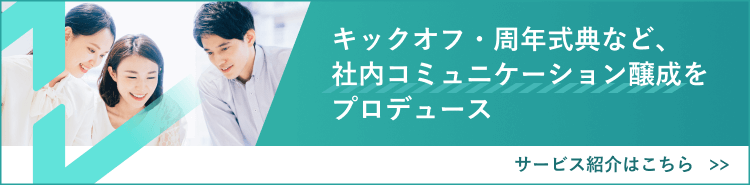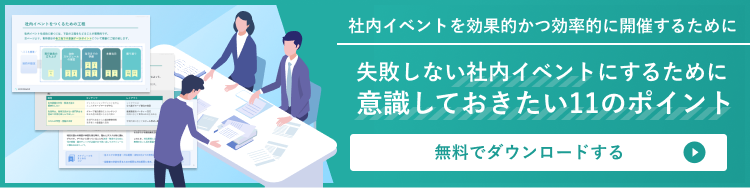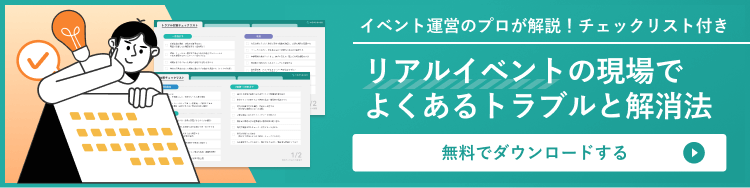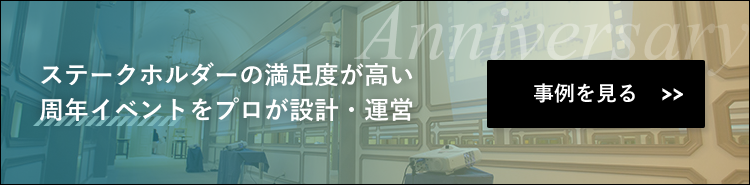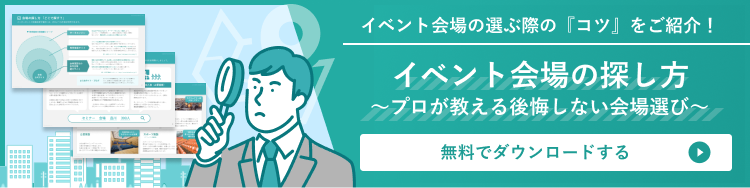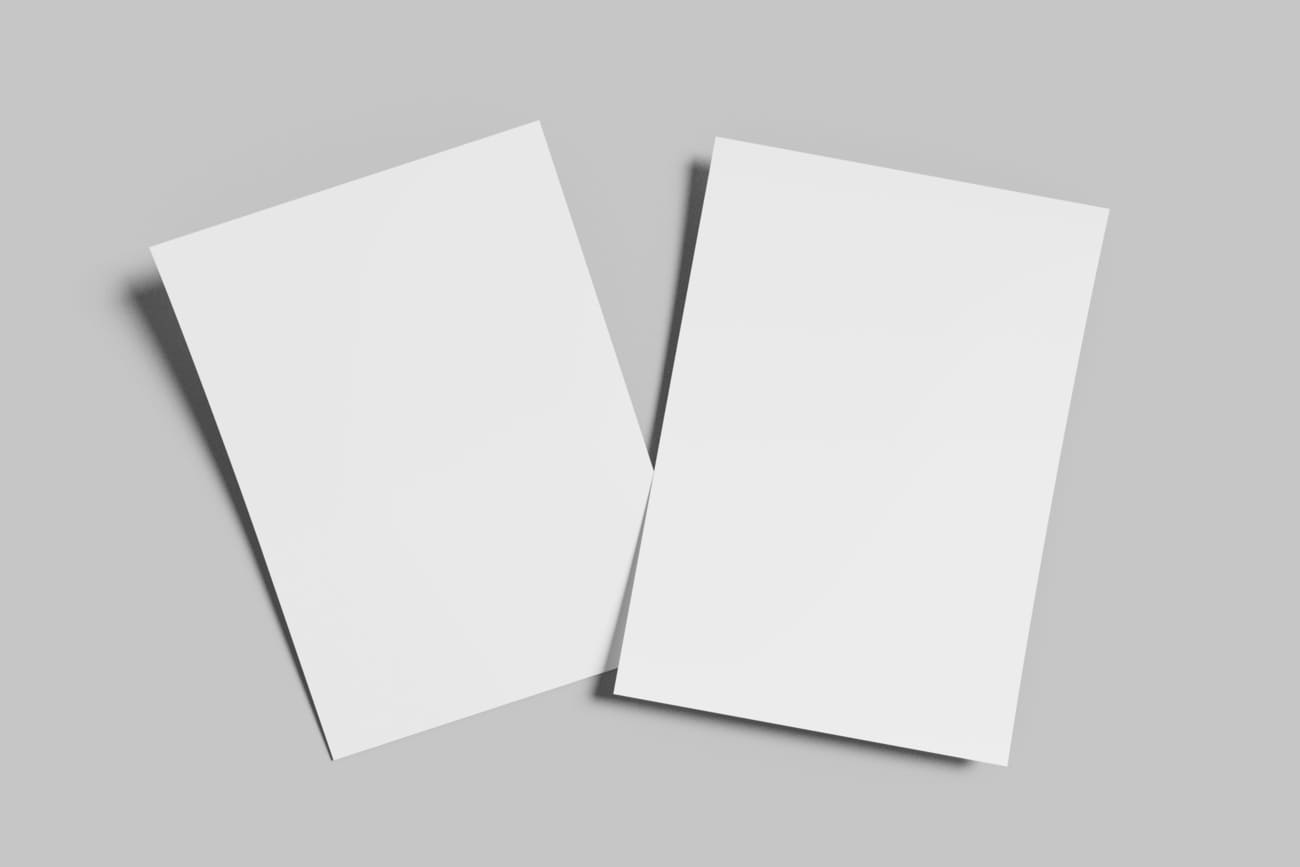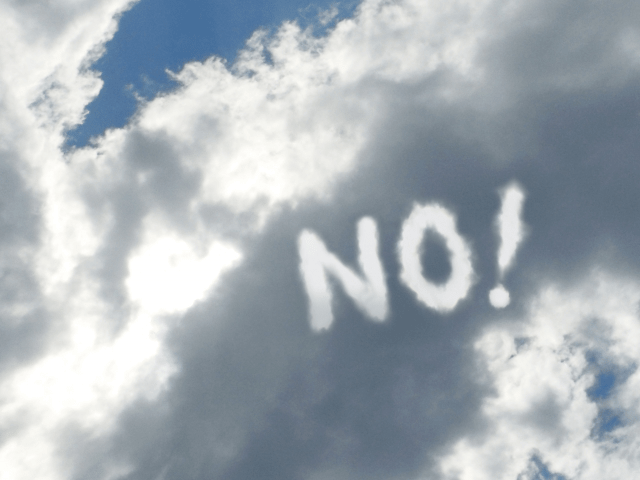式典で使える台本のテンプレートを紹介!成功のために司会が意識すべきポイントも

自社で式典を開催するにあたって、司会を任された場合、どのように進行すればいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、式典で使える台本のテンプレートを紹介します。
式典を成功させるために司会が意識すべきポイントについても解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
式典の基本的な流れについて
式典では、基本的に以下のような流れで開催されます。
- 開会の挨拶:司会者が登壇して式典の開始を宣言する
- 主催者の挨拶:主催者が式典の趣旨や開催への想いについて参加者に述べる
- 来賓の祝辞:招待した来賓からお祝いの言葉やエールをもらう
- 祝電の披露:当日出席できなかった方からの祝電やメッセージを紹介する
- 来賓の紹介:出席している来賓を順番に紹介する
- 中締めの挨拶・謝辞:関係者が謝辞や今後の抱負を述べる
- 閉会の挨拶:司会者が式典の終了を宣言する
上記のほかに竣工式や創立記念式典などであれば、鏡開きやテープカットといった記念行事が行われたり、表彰や記念品を贈呈したりすることがあります。
式典で使える台本のテンプレートを紹介
式典で使える台本のテンプレートについて、以下の順番で紹介します。
- 開会の挨拶
- 主催者の挨拶
- 乾杯
- 表彰状・記念品授与
- 来賓の祝辞
- 祝電の披露
- 来賓の紹介
- 中締めの挨拶・謝辞
- 閉会の挨拶
ぜひ参考にしてみてください。
開会の挨拶
皆さま、本日はご多用の中、〇〇式典にご出席いただき、誠にありがとうございます。
ただいまより、〇〇式典を開催いたします。
本日の司会を務めます、△△でございます。
どうぞ最後までよろしくお願いいたします。
開会の挨拶では、要点を絞ってなるべくシンプルに話しましょう。
ただし、式典名や自身の名前は必ず伝えるようにしてください。
主催者の挨拶
続きまして、主催者を代表いたしまして、〇〇(主催者名・肩書)よりご挨拶を申し上げます。
(挨拶終了後)
ありがとうございました。
社外の来賓を招待している場合には、代表者に対しても敬語を使わないのがマナーです。
主催者の挨拶はあまり長くならないよう、事前に伝えておきましょう。
乾杯
続きまして、祝宴の始まりにふさわしく、乾杯のご発声を〇〇(来賓名・肩書)様にお願い申し上げます。
皆さま、グラスのご準備をお願いします。
〇〇(来賓名・肩書)様、よろしくお願いいたします。
(挨拶終了後)
〇〇様、ありがとうございました。
乾杯の挨拶を行う際には、社内の人物だけでなく、来賓の方の中からお願いしても問題ありません。
表彰状・記念品授与
ここで、日頃のご尽力に感謝し、表彰状および記念品の贈呈を行います。
本日表彰されますのは、〇〇を達成された計△名の方々です。
受賞者の皆さま、どうぞご登壇ください。
皆さま、表彰される方々へ盛大な拍手をよろしくお願いいたします。
(表彰状および記念品の贈呈終了後)
表彰された皆さま、おめでとうございます。
これからもさらなるご活躍を期待しています。
それでは、壇上の皆さまはお席へとお戻りください。
スムーズに進行するよう、受賞者には事前に流れを伝えておきます。
不安であれば、リハーサルを行いましょう。
来賓の祝辞
ここでご来賓を代表して、〇〇(来賓名・肩書)様よりご祝辞を賜りたいと存じます。
(祝辞終了後)
〇〇様、ありがとうございました。
基本的に来賓者の中から代表者1名を選びますが、複数名に依頼しても問題ありません。
祝電の披露
続きまして、ご多忙のためご臨席いただけなかった方々から、心温まる祝電を頂戴しておりますので、幾つかご紹介させていただきます。
(何名かの祝電を読み上げる)
この他にもたくさんの祝電を頂戴していますが、ここからはお名前のみ紹介させていただきます。
祝電が多い場合には、一つずつ読み上げると非常に時間がかかります。
そのため、何名かの祝電を読み上げたら名前だけ紹介するようにしましょう。
来賓の紹介
ここで、ご臨席いただいておりますご来賓の皆さまをご紹介させていただきます。
ご紹介のみとさせていただきますので、お名前をお呼びした際にはご起立のうえ、一礼をお願いいたします。
(来賓の氏名・肩書を順番に紹介)
来賓の方には、一連の流れやタイミングについて、あらかじめ伝えておきましょう。
中締めの挨拶・謝辞
式典も中盤を迎えました。
ここで、〇〇(役職・氏名)より、これまでのご協力への感謝を込めてご挨拶申し上げます。
それでは〇〇(役職・氏名)、よろしくお願いいたします。
(挨拶終了後)
ありがとうございました。
基本的に中締めの挨拶・謝辞については、自社の中で立場が2番目の人が行います。
閉会の挨拶
それでは、以上をもちまして本日の式典を閉会とさせていただきます。
ご参加いただきました皆さまのご健康とご多幸をお祈り申し上げますとともに、今後とも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。
本日はありがとうございました。
式典終了後に祝賀会などを予定している場合には、詳細について必ずアナウンスしましょう。
式典を成功させるために司会が意識すべきポイント
式典を成功させるために司会が意識すべきポイントは、以下の通りです。
- 入念にリハーサルを行う
- タイムスケジュールを管理する
- 登壇者や来賓の名前・肩書を正確に把握する
順番に解説します。
入念にリハーサルを行う
式典を成功させたいのであれば、入念にリハーサルを行うことが大切です。
特にこれまで司会を担当したことがない場合には、尚更です。
最終的に台本を見なくても式典を進行できるよう、一度だけでなく何回もリハーサルを行いましょう。
そうすることで、次第に不安が解消されるはずです。
タイムスケジュールを管理する
式典では、開催時間が決められているため、タイムスケジュールを管理するのも司会の重要な役目となります。
予定よりも進行が早くなっている場合には歓談の時間を長めに確保したり、進行が遅れている場合には内容の一部を省略したりするなど、状況に応じて柔軟に対応しましょう。
登壇者や来賓の名前・肩書を正確に把握する
登壇者や来賓の名前・肩書の読み間違いは非常に失礼な行為にあたります。
読み間違いによって不愉快な思いをさせてしまわないよう、あらかじめ名簿を作成した上で登壇者や来賓の名前・肩書を正確に把握しておくようにしましょう。
心配であれば、フリガナをふっておくのがおすすめです。
式典の開催・運営ならニューズベースにお任せください
式典を開催・運営するにあたって、十分なリソースが必要となるので、「自分たちだけで式典を行えるのか不安」と感じる方もいるはずです。
そのような場合には、株式会社ニューズベースにお任せください。
株式会社ニューズベースでは、イベントプロデュース事業を展開しており、当日までの工程管理から式典当日の運営・撤去作業まで、式典に関するさまざまな業務のサポートをトータルで行っています。
年間400案件以上の運営実績があり、中小企業から大手企業・大学・官公庁まで、業界業種問わずにサービスを提供してきたため、安心して依頼いただくことが可能です。
無料見積もりを行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ
本記事では、式典で使える台本のテンプレートや式典を成功させるために司会が意識すべきポイントについて解説しました。
これから式典を開催するにあたって、司会を任された場合には、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
式典を開催・運営するにあたって何かお困りの場合には、株式会社ニューズベースにお気軽にお問い合わせください。