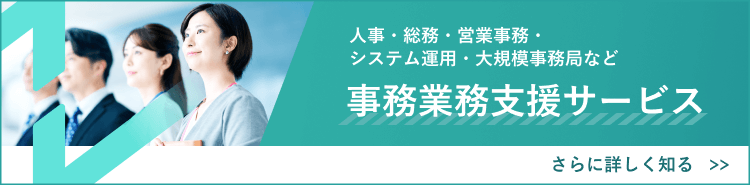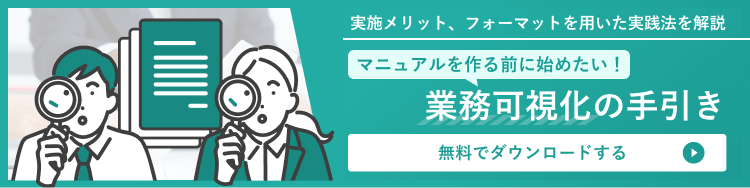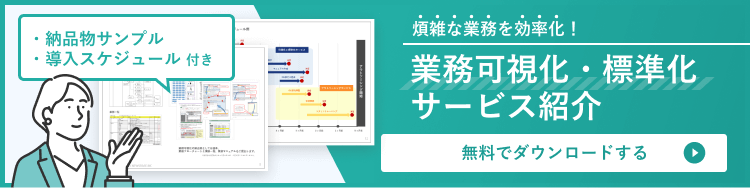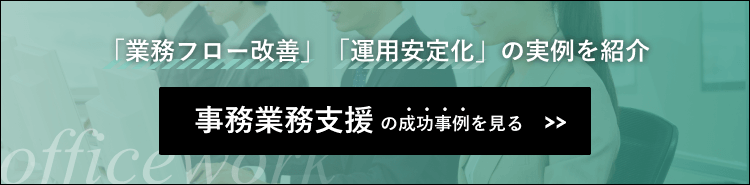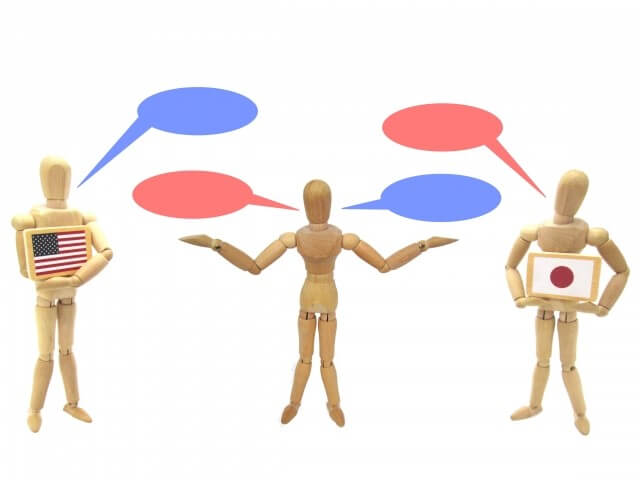業務改善における5S活動とは?メリットや手順について紹介!
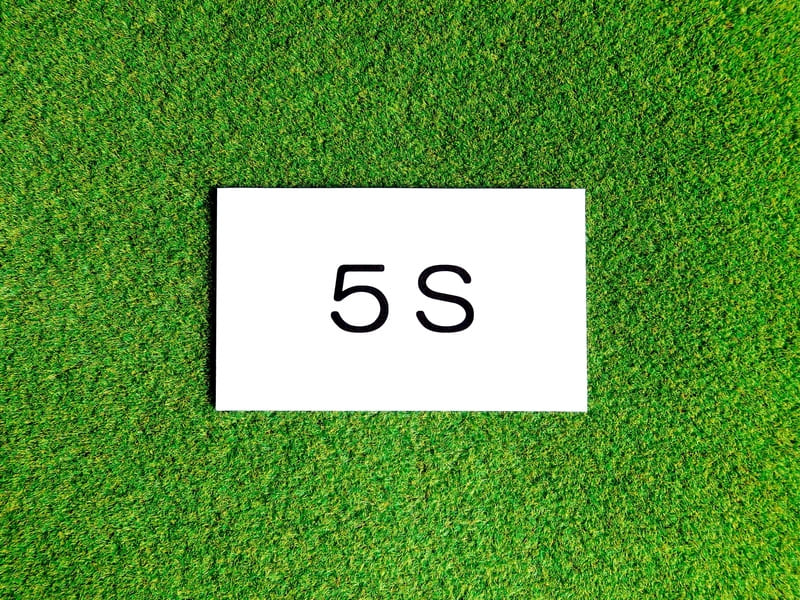
これから業務改善を行うにあたって、必要となるのが5S活動です。
5Sとは、「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「躾」の5つを総称した言葉であり、実際にトヨタ自動車が行ったことで世界中に広がりました。
5S活動を行うことで、コストの削減や生産性の向上などの効果に期待ができます。
そこで本記事では、業務改善における5S活動の詳細やメリット・手順・ポイントについて解説します。
株式会社ニューズベースでは、5Sをはじめとしたさまざまな手法で、業務改善のご支援を行っています。5S活動の現場定着から組織全体の仕組みづくりまで、幅広くサポート可能です。業務改善でお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
目次
業務改善における5S活動
業務改善における5S活動として、以下の5つを紹介します。
- 整理(Seiri)
- 整頓(Seiton)
- 清掃(Seisou)
- 清潔(Seiketsu)
- 躾(Shitsuke)
整理(Seiri)
整理は、必要なモノと不要なモノを区別して不要なモノを処分することを目的としています。書類や備品だけでなく、パソコン内のデータやメール、共有フォルダなども整理の対象です。
整理の意義・目的
- 効率化:必要な資料をすぐに取り出せる
- ミス防止:探し物の時間や作業ミスを削減する
- 快適な職場:オフィスのスペースを有効活用し、快適な環境を実現する
- コスト削減・リスク低減:余分な在庫や古い情報を減らし、コストや情報漏洩リスクを抑える
- 意識向上:職場全体に「無駄をなくす」意識を浸透させる
オフィスでの整理の取組方法例
- デスクやキャビネットの中身を全て出し、本当に使うものだけを戻す
- 書類やデータを「必要」「不要」「保留」に仕分けし、不要なものはすぐに処分
- 共有フォルダやメールボックスも定期的に見直し、古いデータや重複ファイルは削除
- 文房具や消耗品は適正な量だけ管理し、余分なストックは持たない
- 社内マニュアルや顧客リストなども定期的に更新し、古い情報は削除する
不要なモノであるかの判断基準として、以下を参考にしてみましょう。
- 1年以上使用していないか
- 具体的な用途があるか
- 今後使用する予定があるか
整頓(Seiton)
整頓は、必要なモノを誰もが使いやすい状態にすることを目的としています。
整理で不要なものを排除したあと、残したものを定位置・定量・明示で管理するのが整頓の基本です。
- 効率化:探す手間なく必要なものをすぐ取り出せる
- 標準化:誰でも分かりやすい・すぐに使える・戻せる状態をつくる
- ミス防止・管理徹底:戻し忘れや紛失・在庫切れを防ぎ、仕事を効率化する
- 安全性向上:職場の安全性を高め、ミスや事故を減らす
オフィスでの整頓の取組方法例
- デスクや共有スペースの文房具・備品に定位置ラベルを貼り、使ったら必ず元に戻す
- 書類やファイルを分類ラベル・見出し付きで保管し、誰でも一目で分かるようにする
- 共有フォルダやデスクトップのファイルを分類し、ファイル名や保存場所のルールを統一する
- 事務用品や消耗品は決められた場所・数量だけ保管し、在庫が減ったらすぐ補充できる仕組みをつくる
- 配線やOA機器のケーブルもまとめて整理し、ラベルで用途を明示する
トヨタ自動車では、「三定」という方法で整頓しています。
- 定位:モノの置き場所を決める
- 定品:モノの種類を定める
- 定量:必要な数を定める
清掃(Seisou)
清掃は、職場やデスク、共用スペースなどをきれいな状態に保つ活動です。職場環境を清潔に維持するとともに、「職場の異常や不具合を早期に発見する」といった目的もあります。整理・整頓で整えたオフィス環境を、良い状態のまま維持し続けるために欠かせない取り組みです。
清掃の意義・目的
- 快適な職場環境:働きやすさやモチベーションが向上する
- 備品・設備の長寿命化:パソコンやコピー機などの不調や故障を早期に発見できる
- 安全性向上:不要物がないことで転倒・事故リスクを減らす
- 異常の早期発見:設備の故障・不具合・消耗品切れなどの異常を見つけやすくなる
- 社内外への印象向上:来客や取引先に好印象を与えやすい
オフィスでの清掃の取り組み例
- デスク周りやパソコンの拭き掃除を毎日行う
- 書類や備品のほこり・汚れを定期的に拭き取る
- 共有スペースや会議室、休憩室の床やテーブルを掃除する
- ゴミ箱・シュレッダーのごみは毎日決まった時間に回収・廃棄する
- エアコン・換気扇のフィルターやOA機器の清掃も定期的に実施する
- 清掃当番やチェックリストを設けて、担当者が交代で責任を持って実施する
清潔(Seiketsu)
清潔は、「整理」「整頓」「清掃」を行い、綺麗な状態を保つことを目的としています。きれいで整った状態を「一時的なもの」にせず、継続して保つことが大切です。
業種にもよりますが、従業員一人ひとりの身だしなみも清潔の一環であることを覚えておきましょう。
清潔の意義・目的
- 継続性:整理・整頓・清掃で整えた状態を長く維持する
- 標準化:ルール化し、全員が同じ基準で行動できるようにする
- 習慣化:清潔を保つことが個人や組織の習慣となり、職場の質が底上げされる
- 健康・安全の維持:ほこりや汚れ、ウイルスなどの繁殖を防ぎ、社員の健康や職場の安全を守る
オフィスでの清潔の取組方法例
- 整理・整頓・清掃のルールや基準を「社内マニュアル」「掲示物」などで見える化し、誰でも確認できるようにする
- デスクや共用スペースの清掃・片付けを日々の業務や終業時のルーティンに組み込む
- 清掃や片付けの担当者・当番を決めて、責任の所在を明確にする
- 定期的に「5Sチェック」や「職場パトロール」を実施し、基準からのズレや改善点を共有する
- 社員全員で「きれいな状態が当たり前」という意識を持ち、気付いた人がすぐに対応する風土をつくる
躾(Shitsuke)
躾は、5S活動で決めたルールや習慣を、全員が当たり前に守れる職場の風土をつくることです。整理・整頓・清掃・清潔を形だけで終わらせず、日々の行動として定着させることが目的です。
躾の意義・目的
- 継続力:5Sのルールや基準を形だけで終わらせず、毎日守る力を養う
- 習慣化:良い行動や職場環境維持を、意識せずできる「習慣」として根付かせる
- 主体性の醸成:上司や担当者の指示だけでなく、一人ひとりが自発的にルールを守る職場をつくる
- 組織風土の向上:全員が同じ意識で行動することで、信頼感や一体感が生まれ、職場の雰囲気も良くなる
オフィスでの躾の取組方法例
- 5Sのルールや基準を定期的に全員で確認・共有し、守れていない点は改善策を話し合う
- 毎日の終業時や週初めに、5Sチェックリストでセルフチェックを行う
- 朝礼やミーティングで5S活動の進捗や成功事例を共有し、意識付けを図る
- ルール違反や整理・整頓ができていない箇所を指摘し合える職場風土をつくる
- 5S活動の優秀者やチームを表彰・フィードバックする仕組みを取り入れ、モチベーションを高める
5Sの実施にはチェックシートの活用が重要
5S活動を職場に根付かせ、継続的に改善するためには、チェックシートの作成が欠かせません。チェックシートの導入には、以下のような目的があります。
- 5Sそれぞれの取り組み内容やルールを明確にする
- 実施状況を可視化し、客観的に把握できるようにする
- 日々のチェックを習慣化し、5S活動を定着させる
- 抜けやムラの発生を防ぎ、継続的な改善につなげる
- 改善点や課題を早期に発見しやすくする
- チーム全体で共通認識を持ち、協力体制を築くきっかけにする
チェックシートを活用することで、5S活動が「やりっぱなし」や「形だけ」で終わらず、日常業務に自然と組み込まれるようになります。
こうした5S活動の目的を踏まえ、以下で具体的なチェック項目例やチェックシートの作り方について解説していきます。
5Sチェックシートの項目例
| 整理 |
・不要な書類や備品がデスクや共有スペースに放置されていないか |
| 整頓 | ・必要な書類、文房具、備品が指定場所にきちんと置かれているか ・ラベルや表示を行い収納場所が分かりやすくなっているか ・作業しやすい動線に沿った配置になっているか ・必要なものを短時間で取り出せるか ・適切な在庫量であるか ・マニュアルや手順書は最新版であるか |
| 清掃 | ・デスク、OA機器、共用スペースが清潔に保たれているか ・汚れやごみがないか ・汚れや破損はすぐ確認できるか ・清掃スケジュールが守られているか ・清掃用具の整理整頓が行われているか ・異常を発見時に速やかに報告されているか ・清掃記録が適切に記入・管理されているか |
| 清潔 | ・5Sのルールや基準が文書化・共有されているか ・ルール・手順は全従業員に伝わっているか ・チェックや点検は定期的に行われているか ・清掃や整頓の責任分担を明確にしているか ・5Sの実施状況を定期的に評価・改善しているか ・教育・指導の記録が管理されているか |
| 躾 | ・全従業員が5S活動を理解し、自主的に取り組んでいるか ・5Sのルールが守られているか ・新入社員や契約社員などへ5S教育が定期的に行われているか ・リーダーが5S活動の推進役となっているか ・5Sの重要性が周知されているか ・チーム全体で5S活動に協力的な雰囲気があるか |
5Sチェックシートの作り方
5Sチェックシートは、「なぜ評価するのか」「何をチェックするのか」「どうやって評価するのか」を明確にした上で作成します。基本的な流れは次の通りです。
1. 評価目的を明確にする
まず、チェックシートを使う目的(例: 5S活動の定着・標準化、作業効率の改善など)をはっきりさせます。
2. 評価項目を設定する
整理・整頓・清掃・清潔・躾について、職場や業務に合わせて具体的なチェック項目を決めます。
3. 評価基準を決める
「できている・できていない」だけでなく、3段階(良い・普通・悪い)など、達成状況を判断しやすい基準にします。各項目の基準も簡潔に明文化しましょう。
4. レイアウトを設計する
項目ごとにチェック欄や評価欄、コメント欄を設け、誰でも記入しやすいシートにします。
5Sチェックシートは、実際に現場で使う人の声を反映させながら作成・改善していくことが大切です。運用しながら随時、内容を見直しましょう。
業務改善で5S活動を行うメリット
業務改善で5S活動を行うメリットは、以下の通りです。
- コストを削減できる
- 生産性が向上する
- 安全性が高まる
順番に解説します。
コストを削減できる
業務改善で5S活動を行うことによって、不要なモノを購入したり保管したりする必要がなくなります。
また、業務の効率化によって無駄な残業などを減らすことが可能なため、コストの削減につながります。
コストが削減した分を従業員に還元することで、従業員満足度の向上に期待ができます。
生産性が向上する
業務改善において5S活動を行うことで、必要な道具や資料を素早く見つけられるようになります。
これによって生産性が向上し業務時間の短縮につながるため、従業員はワークライフバランスを実現できるようになるはずです。
その結果、これまで以上に働きやすい職場環境となり、定着率の向上につながります。
安全性が高まる
業務改善で5S活動を行うことによって、 清潔で整理された職場環境となるため、事故のリスクが低減し、職場の安全性が高まります。
また、機械のメンテナンス・点検もルーティン化されるため、ミスや不良品の発生が抑えられ、商品やサービスの品質向上にも期待ができます。
業務改善で5S活動を行う際の手順
業務改善で5S活動を行う際の手順は、以下の通りです。
- 目的・ゴールを設定する
- ルールを作成する
- 実践しながらPDCAを回す
一つずつ解説します。
1.目的・ゴールを設定する
業務改善で5S活動を行うにあたって、まずは「なぜ5S活動を行う必要があるのか」「5S活動を行って最終的にどのようにしたいのか」目的・ゴールを設定するようにしましょう。
目的・ゴールともに曖昧に設定してしまうと、途中で方針がブレる恐れがあります。
そのため、「〇〇業務にかかるコストを△%削減する」といった形で、数値を用いてなるべく具体的に設定しましょう。
目的・ゴールを設定したら、その内容を従業員全員に共有します。
2.ルールを作成する
目的・ゴールの設定が完了したら、5Sのルールを作成します。
ルールを作成する際には、現在の職場環境の様子を確認して問題点や課題点を抽出した上で決めましょう。
5Sルールの具体例は、以下の通りです。
- 整理:必要なモノ以外は机に置かない
- 整頓:利用頻度が高いモノはなるべく近くに置く
- 清掃:業務終了後に自身の作業場所を清掃する
- 清潔:少しでも汚れたらその場ですぐに清掃する
- 躾 :ルールを守らない従業員に対しては上長が注意する
現場の状況を知らない上層部がルールを作成してしまうと、従業員から不満の声が挙がる恐れがあります。
そのような事態を防ぐためにも、従業員全員が参加してルールを決めるようにしましょう。
3.実践しながらPDCAを回す
ルールを作成したら、5S活動を実践します。
実践することで、新たな問題や課題が出てくるはずです。適宜話し合いを行い、改善していきましょう。
実践しながらPDCAを回すことで、効果的な5S活動となります。
5Sが失敗する原因と対策
5S活動は導入しても「続かない」「形だけで終わる」など、失敗するケースも少なくありません。失敗につながるよくある要因と、その対策を紹介します。
・原因1:備品や書類の置き場所が曖昧になっている
対策:全てのものに「定位置」を決め、全員でルールを共有する。
・原因2:使い終わったものが元の場所に戻されない
対策:使用後は必ず元の場所へ戻すことを習慣化し、徹底する。
・原因3:人によって収納や管理の方法がバラバラ
対策:保管方法や手順を職場で統一し、誰でも分かるようルール化する。
・原因4:従業員が自発的に取り組めない
対策:5Sの目的やメリットをしっかり伝え、現場の意見も取り入れながら一人ひとりが主体的に参加できる雰囲気をつくる。
・原因5:5Sの成果や改善状況が見える化されていない
対策:チェックシートや掲示物などを活用し、進捗や成果を「見える化」して共有する。
・原因6:5Sのルールや基準が曖昧で判断や実行が人によって異なる
対策:ルールや基準を具体的に明文化し、全員で共有・徹底する。
まとめ
本記事では、業務改善における5S活動の詳細やメリット・手順・ポイントについて解説しました。
5Sとは、「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「躾」の5つを総称した言葉であり、業務改善で5S活動を行うことで、コストの削減や生産性の向上などに期待ができます。
手順についても詳しく解説しておりますので、これから業務改善を行うにあたって5S活動を検討しているのであれば、本記事を参考にしてみてください。
業務改善を行うにあたって、人手不足やリソース不足にお困りの場合には、株式会社ニューズベースにお任せください。
株式会社ニューズベースでは、事務業務支援サービスを提供しており、業務マニュアルの作成や問い合わせ対応・データ入力・営業資料の作成など、さまざまな業務のサポートを行っています。
そのため、株式会社ニューズベースが提供している事務業務支援サービスを活用することで、現状のリソースを業務改善に割くことが可能です。
これまで中小企業から大手企業・大学・官公庁まで、業界業種問わずにサービスを提供してきたため、安心して依頼いただけます。
無料見積もりを行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。